
沖縄でキャバクラを開業したいけれど、「営業許可の取り方がわからない…」「風俗営業の条件って何?」とお悩みではありませんか?
キャバクラを営業するには【風俗営業1号許可】【飲食店営業許可】【消防法上の届出】の3つの許可が必要です。しかもそれぞれに細かい条件があり、理解しないまま進めると、申請が通らず開業が遅れてしまうことも。
実際に、キャバクラ経営者の中には「もっと早く専門家に相談しておけば…」という声を漏らす方も少なくありません。
本記事では、沖縄でキャバクラを開業する際に必要な許可の種類や取得条件をわかりやすく解説。さらに、どんな準備が必要で、どのように進めるべきかをご紹介します。
「許可のことで失敗したくない」「スムーズに開業したい」と考えているあなたに、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。
まずは、キャバクラ開業に欠かせない3つの許可から見ていきましょう。
キャバクラ開業に必要な3つの許可
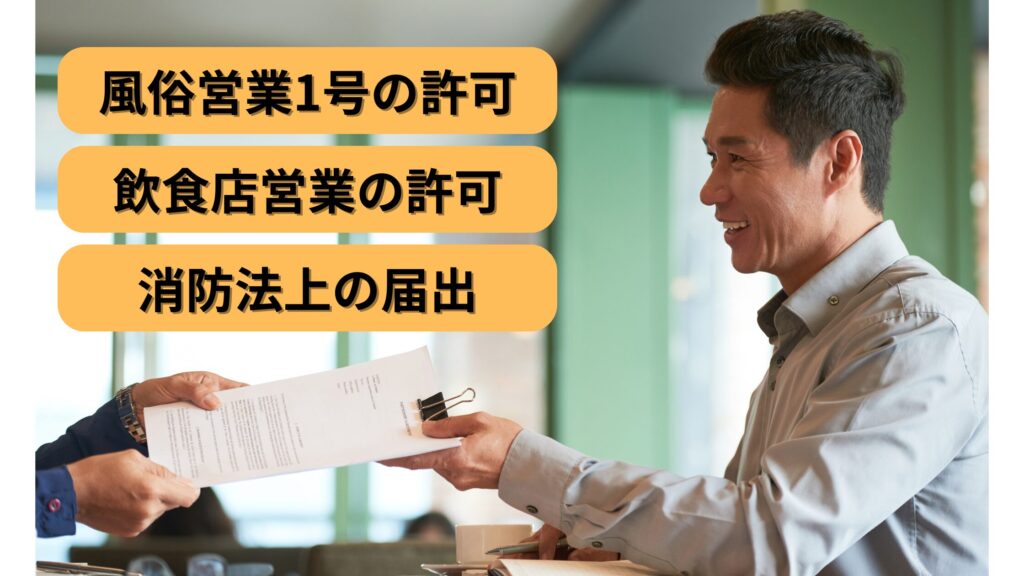
キャバクラを営業するには、単にお店を用意すればいいというわけではありません。
法律上、営業を始めるには3つの許可を取得する必要があります。
それが「風俗営業1号の許可」「飲食店営業の許可」「消防法上の届出」です。
それぞれ異なる役所に申請が必要で、満たすべき条件もバラバラです。
このセクションでは、それぞれの許可の概要と、取得するために必要な要件をわかりやすくご紹介します。
スムーズに開業準備を進めるために、まずは各許可の特徴を押さえておきましょう。
風俗営業1号の許可
キャバクラ営業には「風俗営業1号」の許可が必須です。
これは、接待を伴う飲食サービスを提供する店舗に求められる営業許可のことです。
この許可を得るには、店舗の立地が用途地域に適合していることや、保全対象施設(学校・病院など)から一定の距離があることが条件です。
また、図面の整備や照度、広さなど、店舗内の構造も基準を満たしている必要があります。
警察署への申請書類には、住民票・登記簿・誓約書・図面など多くの書類が必要で、内容にも細かな注意が必要です。
さらに、欠格事由に該当する場合(過去に風営法違反があるなど)は許可が下りません。
このように、条件や書類が非常に複雑なため、専門家のサポートを受けるのが現実的といえるでしょう。
飲食店営業の許可
キャバクラといえども飲食を提供する以上、「飲食店営業許可」も必要です。
これは保健所が管轄しており、店舗が衛生管理の基準を満たしているかを確認します。
許可を得るには、厨房設備、手洗い場、換気システムなどが整っていることが条件です。
また、「食品衛生責任者」を設置する必要があり、資格がない場合は講習の受講が求められます。
申請には店舗の図面や営業設備の内容を記した書類などが必要で、現地調査もあります。
基準を満たしていないと再申請になり、開業が遅れることもあるため注意が必要です。
風俗営業の許可とは別に保健所への対応も必要なので、スケジュール管理が重要になります。
消防法上の届出
店舗を新たに使用する際は、「防火対象物使用開始届出書」の提出が義務付けられています。
これは消防署への届出で、火災予防や避難の安全性を確保するための制度です。
具体的には、消火器や誘導灯、非常口などの設置が基準に適合している必要があります。
さらに、一定の広さや従業員数によっては「防火管理者」の選任が求められるケースもあります。
届出後には消防署による立入検査が行われ、基準を満たしていない場合は改善指導が入ります。
対応が遅れると開業予定日に間に合わない恐れもあるため、余裕を持った準備が重要です。
火災リスクを最小限に抑えるための届出であり、安全な営業の第一歩といえるでしょう。
各許可を取得するための基本的な流れ
キャバクラ開業に必要な3つの許可は、それぞれ別の窓口に申請する必要があり、取得の順番やタイミングも重要です。
まず、内装工事の前に店舗図面を用意し、用途地域や立地条件を確認します。
その上で、風俗営業の許可を警察署へ、飲食店営業の許可を保健所へ、消防法の届出を消防署へ提出していきます。
多くの場合、飲食店営業許可→消防法届出→風俗営業許可の順で進めるのが効率的です。
ただし、自治体ごとにローカルルールがあるため、事前に確認が必要です。
書類作成・提出・立入検査・結果待ち…と各手続きには時間がかかります。
本業と並行して対応するのは大変なため、行政書士に依頼してスムーズに進めるのが現実的です。
風俗営業1号許可の取得条件
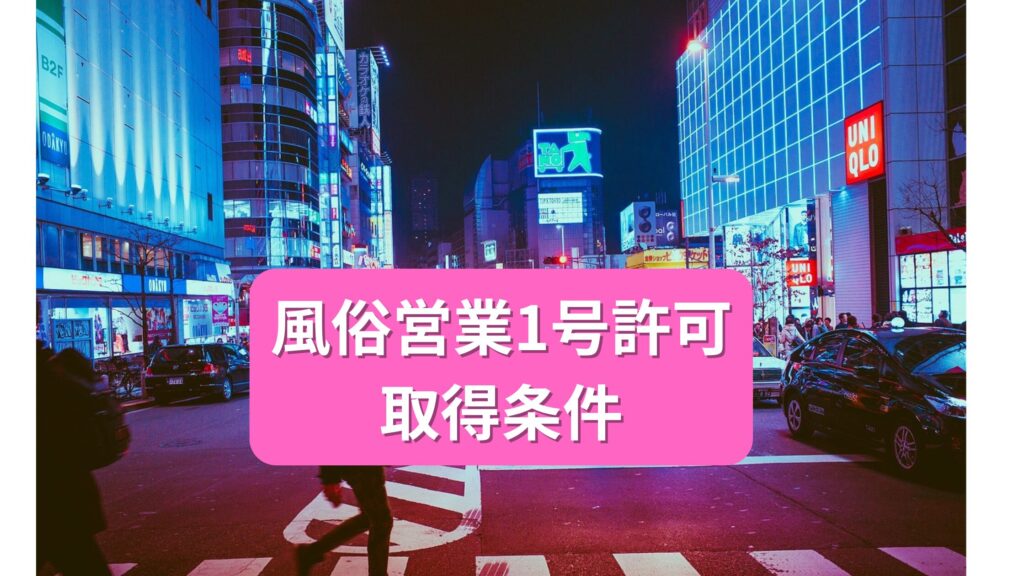
風俗営業1号許可を取得するには、複数の厳しい条件をクリアする必要があります。
なかでも重要なのが、営業所の「立地条件」「管理者の人的条件」「施設・設備要件」の3つの視点です。
さらに、それらを満たした上で、所轄の警察署へ書類を提出し、審査を受ける必要があります。
このセクションでは、それぞれの条件をわかりやすく解説していきます。
営業所の立地条件(用途地域・保全対象施設との距離制限)
風俗営業1号許可では、営業所の立地に関する制限が特に厳しく設定されています。
なぜなら、風俗営業は周辺環境に与える影響が大きいため、地域のルールを守ることが前提だからです。
具体的には、キャバクラを開業できるのは「商業地域」や「近隣商業地域」などに限られます。
さらに、学校や病院、図書館などの保全対象施設から一定の距離(原則100m以上)を確保しなければなりません。
この距離制限は、自治体ごとに細かい違いがあるため、事前に市役所や警察署で確認が必要です。
条件を満たさない場所で営業申請をしても、許可は下りません。
物件選びの段階から立地条件を確認することが、開業準備の第一歩といえるでしょう。
管理者の人的条件(欠格事由の確認)
風俗営業を行うには、営業所に1人「管理者」を選任しなければなりません。
この管理者には厳格な人的要件があり、欠格事由に該当する場合は許可が下りないことになっています。
欠格事由とは、たとえば過去5年以内に風営法違反や暴力団関係の処罰を受けたことがある人などです。
また、成年被後見人や破産者で復権していない人も該当します。
仮に申請者本人に問題がなくても、実質的に店舗を経営する人物が欠格に該当していると判断された場合も、申請は却下される可能性があります。
したがって、誰を管理者に据えるかは非常に重要です。
身分証や住民票、誓約書などを準備して、書類上でも問題がないことを明確に示す必要があります。
営業所の施設・設備要件
営業所の内部構造や設備にも、風俗営業1号許可ならではの細かい基準があります。
これは、利用者の安全や、近隣への配慮を目的としたルールです。
たとえば、接客室の照度は10ルクス以上でなければならず、個室化を防ぐための構造(見通しの確保)も必要です。
また、従業員専用の控室やトイレ、待機スペースなどが適切に設置されていることも求められます。
さらに、客室の出入口の数や、床面積の広さについても細かな基準があります。
図面の不備や実際の構造と違う部分があると、現地調査で問題視される可能性があります。
内装工事の前に、行政書士などと連携しながら基準を満たした設計を行うことが、スムーズな許可取得の鍵となります。
警察署への申請手続きと所要期間
風俗営業1号許可の申請は、営業所を管轄する警察署の「生活安全課」で行います。
この手続きには多くの書類が必要で、準備と提出に時間と労力がかかります。
提出書類には、申請書・営業所の詳細図面・管理者の住民票・誓約書・履歴書・用途地域証明書などが含まれます。
提出後は、警察による書類審査と現地調査が行われます。
申請から許可が下りるまでの期間は、原則として55日以内とされています。
しかし、書類に不備があった場合や補正が必要な場合は、さらに日数がかかることがあります。
本業をこなしながらこれらの手続きを進めるのは難しいため、行政書士に依頼する方が確実でスピーディです。
スムーズな開業を目指すなら、早めの準備と専門家の活用が成功への近道です。
手続き先となる警察署は営業所の所在地によって異なります。各警察署の管轄地域は下記の参考サイトから確認できますのでご覧ください。
飲食店営業許可の取得条件
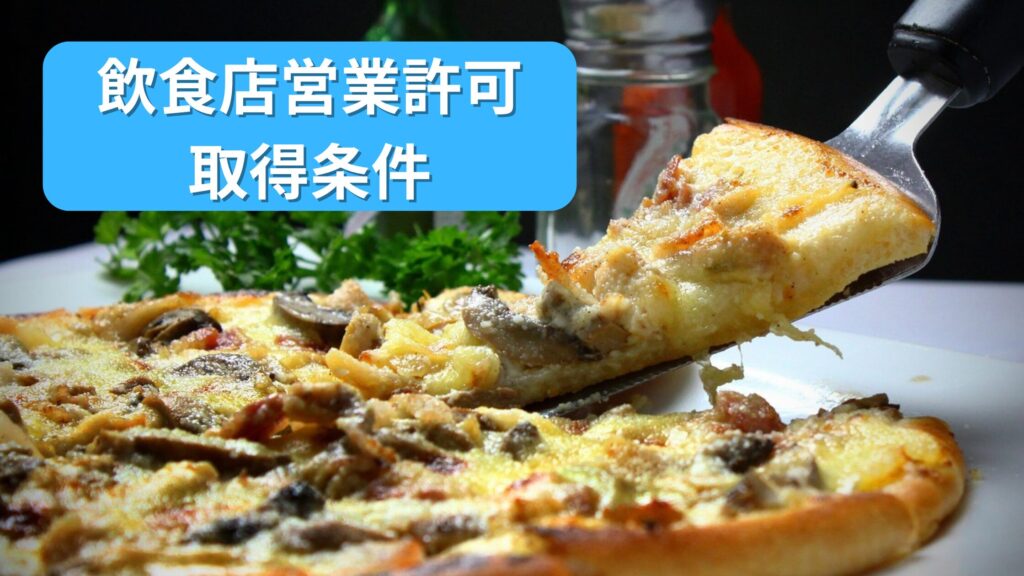
キャバクラでお酒や軽食を提供するには、「飲食店営業許可」の取得が必須です。
この許可は、管轄の保健所が施設の衛生面や運営体制をチェックした上で発行されます。
許可を得るためには、厨房や手洗い場などの設備が基準に適合していることに加え、「食品衛生責任者」の設置が求められます。
このセクションでは、飲食店営業許可に必要な施設の条件や責任者の要件、申請に必要な書類と流れについて、わかりやすく解説します。
保健所で求められる施設や設備の条件(厨房・手洗い・換気など)
飲食店営業許可を取得するには、店舗の施設や設備が衛生基準を満たしている必要があります。
これは食中毒や感染症を防ぎ、安全な食環境を確保するための重要なポイントです。
具体的には、十分な広さの厨房があり、衛生的な手洗い場が設置されていること。
さらに、換気設備、洗浄シンク、冷蔵庫などが適切に設置され、清掃しやすい内装材が使われていることが求められます。
設備が不十分な場合、保健所の現地調査で不適合と判断され、再工事や申請やり直しになるケースもあります。
そのため、内装工事の前に、事前相談で図面を持ち込むなどの準備が推奨されます。
保健所の基準に沿った設計を行うことが、スムーズな営業許可取得の第一歩です。
責任者の人的条件(食品衛生責任者の資格)
飲食店営業には、必ず「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。
この資格がないまま営業を開始することはできません。
食品衛生責任者とは、店舗の衛生管理を担う人物であり、従業員への指導や衛生チェックを行う役割を担います。
調理師や栄養士などの有資格者であれば、自動的にこの資格に該当します。
資格がない場合でも、所定の講習を受講すれば誰でも取得が可能です。
そのため、早めに講習のスケジュールを確認し、受講しておくことが重要です。
責任者の不在や無資格は営業停止処分の対象になることもあるため、万全の体制を整えておきましょう。
食品衛生責任者講習の受講要件
食品衛生責任者講習を受けるには、特別な資格や実務経験は必要ありません。
18歳以上であれば、誰でも受講することができます。
これにより、調理経験がないオーナーや店舗責任者であっても、事前に講習を受けておけば営業に支障はありません。
講習の所要時間は1日(6時間程度)で、修了すれば即日で資格証が交付されます。
予約枠はすぐに埋まることが多いため、開業スケジュールに余裕を持って申し込むことが大切です。
特に沖縄など地方都市では、月に数回しか開催されないこともあります。
スムーズな開業のためにも、物件契約や工事と並行して早めの受講をおすすめします。
食品衛生責任者講習の受講方法
食品衛生責任者講習の受講方法は、各都道府県の食品衛生協会で案内されています。
沖縄県内では、各地域の保健所や協会が実施する講習会に事前予約して参加する形式が一般的です。
申し込みはWebフォームまたは窓口で行い、受講料(沖縄では概ね10,000円前後)を支払います。
当日は、身分証明書を持参し、講義と確認テストを受ければ、その場で資格が与えられます。
最近では、自治体によってはオンライン講習に対応している場合もあります。
ただし、講習の認定対象や実施形式は地域により異なるため、事前に公式サイトを確認することが必要です。
確実に資格を取得するには、地域のルールに沿った手順で手続きを進めることが大切です。
必要書類と申請の手順
飲食店営業許可を取得するには、所定の書類を保健所へ提出する必要があります。
書類に不備があると申請が受理されないため、正確な準備が欠かせません。
主な必要書類は、営業許可申請書、店舗の平面図・設備図、登記事項証明書(法人の場合)、水質検査成績書(井戸水使用時)などです。
また、食品衛生責任者の資格証明書や、本人確認書類も必要になります。
提出後、保健所の職員による現地調査が行われ、基準を満たしていれば許可証が発行されます。
申請から許可までの期間は、通常1週間〜10日前後が目安です。
提出タイミングや工事の進行具合によっては開業が遅れることもあるため、早めの準備と段取りが重要です。
消防法上の届出と条件

キャバクラを開業する際には、消防法に基づく各種の届出や設備設置が必要です。
なぜなら、万が一の火災から従業員やお客様の命を守るため、一定の安全基準を満たす義務があるからです。
たとえば、消防用設備の設置や、防火管理者の選任といった手続きが求められます。
これらを怠ると、営業開始が遅れたり、行政指導を受ける可能性もあります。
以下で、キャバクラ開業時に必要となる主な消防法上の届出や条件を、具体的にわかりやすく解説します。
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
キャバクラなどの店舗では、スプリンクラーや火災報知器などの消防設備の設置が必要です。
特に客席部分の床面積が300㎡を超える場合、特殊消防用設備の設置が義務付けられます。
これらを設置する場合は、工事着手前に「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」を所轄の消防署に提出する必要があります。
届出を怠ると、指導の対象になるだけでなく、安全性の面でも大きなリスクを抱えることになります。
設備業者と連携しながら、確実に書類提出を行いましょう。
防火対象物使用開始届出
店舗として使用を開始する際には、「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。
これは、建物内で新たに人が集まる施設として利用を始める場合に義務付けられています。
具体的には、営業を開始する7日前までに所轄の消防署に届け出なければなりません。
仮に届出を忘れてしまうと、消防の立ち入り検査に支障が出る可能性があります。
開業準備で忙しい中でも、届け出の期限と内容をしっかり確認し、スケジュールに組み込んでおくことが重要です。
火を使用する設備等の設置届出
店舗で厨房機器などの火を使用する設備を設置する場合は、「火を使用する設備等の設置届出書」の提出が必要です。
これは、火災リスクが高まる設備を使用する際の安全管理の一環です。
届出は、設備を使用開始する7日前までに消防署へ提出します。
たとえば、ガスコンロやグリラーを設置する場合が該当します。
忘れると営業停止や是正命令につながる恐れもあるため、設置のタイミングと併せて必ず届け出ましょう。
防火管理者選任届出
キャバクラなどの一定規模以上の店舗では、防火管理者を選任し、「防火管理者選任届出書」を提出しなければなりません。
これは、火災予防体制を整えるための法律上の義務です。
収容人員が30人以上の場合などに適用され、選任された防火管理者は、避難訓練の実施や日常的な安全点検の責任者となります。
届出の期限は選任後速やかに。
防火管理者講習を受講して資格を取得する必要があるため、早めにスケジュールを調整しましょう。
キャバクラ店での設置が義務付けられている消防設備
キャバクラでは、消防法によりいくつかの消防設備の設置が義務づけられています。
たとえば、自動火災報知設備、誘導灯、消火器などが挙げられます。
これらの設備は、万が一の火災時に迅速な避難や初期消火を可能にし、被害を最小限に抑える役割を果たします。
設置義務は、店舗の規模や構造によって変わるため、事前に消防署と相談しながら確認することが大切です。
設備の未設置は営業停止や罰則の対象になることもあるため、絶対に見落とさないようにしましょう。
許可を取った後に気をつけたいこと

キャバクラの営業許可を取得しても、それで終わりではありません。
許可後も、法律や行政のルールを守って営業を続ける必要があります。
たとえば、営業時間の制限、営業許可証の掲示義務、キャッチ行為の禁止など、
違反すれば指導や処分の対象となる決まりが多数あります。
特にキャバクラは、行政の監視が強い業種です。
「うっかりしていた」では済まされないこともあるため、
日々の営業でも法令遵守の意識を持つことが大切です。
ここでは、許可取得後に気をつけたい5つのポイントを解説します。
営業時間の遵守
キャバクラの営業には、風営法によって定められた営業時間があります。
基本的に、風俗営業1号許可を受けた店舗は深夜0時までしか営業できません。
この制限を守らずに営業を続けると、営業停止や許可の取消処分を受ける可能性があります。
「ちょっとだけ延長」といった安易な判断が、大きなリスクを生むのです。
そのため、営業時間はスタッフ全員が正確に把握し、
閉店作業も含めて余裕を持ってスケジュールを組むことが重要です。
確実に許可時間内で営業を完結させる体制を整えましょう。
営業許可証の掲示
営業許可を受けたら、店内の見やすい場所に「営業許可証」を掲示する必要があります。
これは風営法で義務づけられており、怠ると行政からの指導対象となります。
許可証の掲示は、行政だけでなくお客様への信頼感にもつながります。
「きちんと許可を得ている安心なお店」であることを示す、大切な情報だからです。
掲示位置は、入り口付近やフロントなど、誰でも目につきやすい場所を選びましょう。
許可証が破損したり汚れたりした場合は、速やかに再交付の手続きを行ってください。
キャッチ(客引き行為)の禁止
那覇市や沖縄市の歓楽街では、キャッチ行為が条例などにより原則禁止されています。
キャバクラも例外ではなく、客引き行為をすれば罰則の対象となります。
客引きが発覚すれば、警察の指導や営業停止命令につながることもあります。
店舗のイメージダウンだけでなく、長期的な営業リスクにもなりかねません。
集客は、SNSの活用や広告、口コミなど、合法的な方法で行うことが大切です。
スタッフ教育を徹底し、「うちの店はキャッチをしない」と明確にルールを伝えましょう。
営業形態の厳守
許可を受けた営業形態と異なるサービスを提供することは、違法行為になります。
たとえば、1号営業で「接待」が認められているからといって、過度なサービスを行うのは危険です。
風営法の「接待」は、客の隣に座って談笑するなどに限られます。
ボディタッチや過剰なサービスは、風俗営業の範囲を逸脱する恐れがあります。
営業形態を守らないと、警察の立入検査で違反を指摘され、許可取消や罰則につながる可能性があります。
提供するサービスの範囲を再確認し、スタッフにも明確にルールを周知しましょう。
無許可営業がバレたら?罰則と営業停止のリスク
許可を得ずにキャバクラ営業を行った場合、「無許可営業」として厳しい罰則が科されます。
具体的には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
※2025年6月の風営法改正により、これまで以上に罰則が強化されています。法改正後の罰則は「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金」です。
さらに、摘発された場合は即時営業停止となり、その後の許可取得も極めて難しくなります。
過去の違反歴は、申請時に不利に働くからです。
「とりあえず営業を始めて、あとで許可を取ろう」という考えは非常に危険です。
開業前には必ず必要な許可を取得し、合法的に営業を始めることが鉄則です。
参考:警察庁|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の 一部を改正する法律(概要)
キャバクラ開業は専門家に任せるのが安心な理由

キャバクラ開業にあたっては、風俗営業許可をはじめとする多くの手続きが必要になります。
中でも「風俗営業1号許可」は、警察署や保健所など複数の役所をまたぐ申請が必要で、想像以上に時間と手間がかかります。
さらに、申請書類は専門的な内容が多く、少しのミスでも受理されなかったり、許可取得が遅れたりするリスクがあります。
スムーズな開業を目指すなら、行政書士などの専門家に依頼するのが最善の選択です。
以下では、キャバクラ開業における準備の大変さと、専門家に任せるメリットについて詳しく解説します。
開業までにかかる時間と手間
キャバクラを開業するには、風俗営業許可を取得するまでに最低でも2〜3ヶ月の準備期間が必要です。
申請前の調査・書類作成・内装工事など、多岐にわたる作業があるため、時間的にも精神的にも大きな負担になります。
許可申請には、営業所の図面や店舗の用途地域の確認など、専門的な知識が求められるうえ、警察署との事前相談や管轄市町村との調整も必要です。
その都度対応するには、かなりの労力と時間がかかります。
たとえば、図面が要件を満たしていないと申請が受理されないため、再提出が発生して開業時期が遅れるケースもあります。
限られた時間の中で開業準備を進めるには、事前に必要なスケジュール感を把握し、計画的に動くことが不可欠です。
書類作成や役所対応のハードル
風俗営業許可の書類作成と役所対応は、専門的かつ厳格なルールに基づいており、一般の方には非常にハードルが高い作業です。
申請書類には、間取り図や営業の詳細、申請人の経歴など多くの情報が求められます。
これらを正確に揃えるには、法令や行政手続きに関する知識が必要です。
用途地域の確認で対象エリア外と判定されたり、保健所との連携不足で営業許可が遅れたりするケースもあります。
役所ごとにルールや対応も異なるため、何度も足を運ばなければならない場面も少なくありません。
スムーズに開業したいなら、煩雑な手続きを一人で抱え込まず、確実に処理できる体制を整えることが重要です。
行政書士に依頼するメリットとは?
行政書士に依頼すれば、煩雑な手続きや役所対応を代行してもらえるため、安心して本業の準備に集中できます。
行政書士は、風俗営業許可に関する知識や申請実績が豊富で、各自治体の傾向や注意点も熟知しているからです。
書類作成や図面のチェック、警察署との折衝など、手続きのすべてをサポートしてくれます。
たとえば、初回の相談時に必要な条件やリスクを丁寧に説明してくれるため、見通しを持ったうえで開業準備が進められます。
また、審査を通すための書類の完成度も高く、申請から許可取得までの期間を短縮できる可能性もあります。
プロに任せることで、ミスやトラブルのリスクを減らせるうえ、最短での開業が実現しやすくなります。
キャバクラ開業は「許可条件の理解」と「専門家の力」がカギ
キャバクラを沖縄で開業するには、「風俗営業1号許可」が必要不可欠です。
しかしこの許可取得には、立地や構造など複雑な条件が絡むため、正しく理解していないとスムーズに進みません。
とくに「許可が出ない立地だった」「図面に不備があってやり直しになった」といったつまずきは非常に多く、開業計画そのものに大きな影響を与えます。
時間や費用を無駄にしないためにも、最初から専門家の力を借りるのが賢明です。
たとえば行政書士であれば、警察署とのやり取りや必要書類の作成を代行してくれますし、要件に適合するかどうかの事前チェックも可能です。
実際、許可取得でつまずかない人の多くは、行政書士と連携して準備を進めています。
沖縄でのキャバクラ開業は、地域特有の制限やルールもあるため、専門的なサポートが成功の近道。
「調べてもよくわからない」「本当にこの場所で営業できるか不安」と感じた時点で、行政書士に相談することをおすすめします。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

