
「キャバクラを始めたいけれど、何から手をつければいいのか分からない……」
そんな不安をお持ちではありませんか?
沖縄でキャバクラを開業するためには、単にお店を作るだけでは済みません。保健所の飲食店営業許可、警察署の風俗営業許可、さらには消防署への届出など、複数の手続きと厳しい審査があなたを待ち受けています。
たしかに、事業を開始する前には「何を、いつ、どこで、どう申請するのか」全く分からず、頭を抱える経営者も多いものです。手続きの順番を間違えて、オープン日がずれ込みそうになることもるでしょう。
ですがご安心ください。このブログでは、キャバクラ開業に必要な許可や手続きの流れ、注意点、そして行政書士のサポート活用法までを、わかりやすく段階的に解説します。
時間と手間のかかる手続きを専門家に任せることで、あなたは「お店作り」や「集客」に集中することができるのです。
「無許可営業で営業停止に……」なんて事態を防ぐためにも、まずはこの記事で正しい知識と準備の方法を手に入れてください。
沖縄でキャバクラを開業するには?|必要な手続き全体の流れ
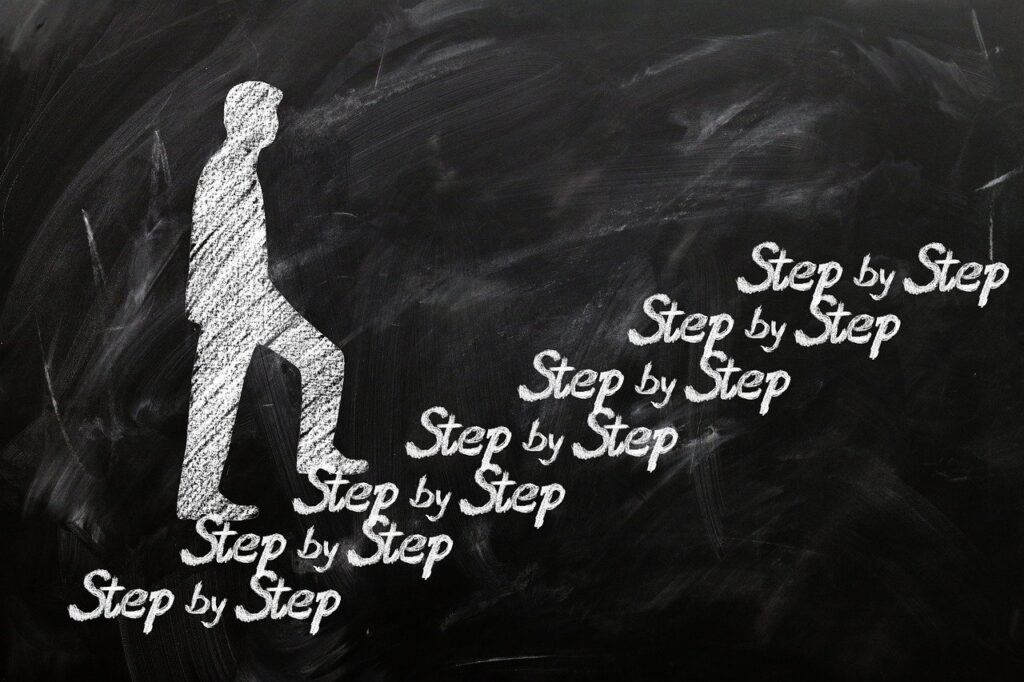
キャバクラの開業には「お店をつくる」こと以上に、法律上のさまざまな手続きを正しく行うことが重要です。
飲食店として営業するための保健所手続きから始まり、風俗営業許可の取得、施設検査や構造基準のチェックなど、複数の行政機関とのやり取りが必要になります。
手順を誤ると、オープン時期が遅れるだけでなく、営業自体ができなくなるリスクも。
この章では、開業前に必ず押さえておきたい主要な手続きの流れを、順を追ってわかりやすくご紹介します。
保健所への相談
キャバクラ開業を考え始めたら、まず保健所への相談からスタートしましょう。
というのも、キャバクラは「飲食店営業許可」が必要な業種だからです。
営業許可を取得するには、厨房や客席などの施設が衛生基準を満たしていることが条件となります。
そのため、店舗の設計段階から保健所に相談し、基準に適合するよう助言を受けることが大切です。
事前相談をしておくことで、後から設計のやり直しが発生するリスクを防げます。
手戻りを避けてスムーズに進めるためにも、保健所への早めの相談が成功への第一歩です。
飲食店営業許可の申請
店舗の図面が整い、工事も完了したら、いよいよ「飲食店営業許可」の申請です。
これは保健所に対して提出し、営業前に必ず取得しなければならない許可です。
申請には、店舗の図面や設備の詳細、営業者の情報など複数の書類が必要です。
申請から許可が下りるまでには、通常1週間程度かかります。
重要なのは、許可が下りる前に営業を始めると法律違反になるという点。
ですので、スケジュールには余裕をもって手続きを進めましょう。
飲食店営業許可はキャバクラ営業の「土台」となる許可です。
確実な申請と計画的なスケジュール管理が求められます。
施設検査
飲食店営業許可の申請後、保健所による「施設検査」が行われます。
これは、提出した図面どおりに設備が整備され、衛生基準に適合しているかを確認するためのものです。
検査では、厨房の換気、手洗い場の設置、床や壁の材質、ゴミの保管方法などがチェックされます。
万が一、基準に適合していない箇所があれば、修正して再検査となることも。
施設検査は、飲食店としての営業可否を左右する重要な工程です。
開業スケジュールに影響を与えないよう、事前に基準を理解し、万全の準備を整えておくことが大切です。
風俗営業許可の申請
キャバクラの営業には、風営法に基づく「風俗営業1号許可」が必須です。
これは所轄の警察署を通じて公安委員会に申請する必要があり、飲食店許可とは別に取得しなければなりません。
申請には、店舗図面や照明・音響設備の仕様、営業者の身分証明や経歴書など多くの書類が求められます。
審査には通常2か月前後かかるため、早めの準備が欠かせません。
風俗営業許可が下りる前に営業を開始すると、重大な行政処分の対象となります。
リスクを回避し、安全に営業を始めるためにも、行政書士などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
構造検査
風俗営業許可申請の過程で、「構造検査」という重要なステップがあります。
これは、店舗が風営法の構造基準に適合しているかを確認するための検査です。
構造検査では、客室の広さ、パーテーションの高さ、出入り口の構造、照度(照明の明るさ)などが細かくチェックされます。
構造基準を満たしていないと、許可が下りないだけでなく、改装工事が必要になるケースも。
この検査は、営業形態に合った設計ができているかの「最終関門」といえるでしょう。
トラブルを防ぐためには、設計段階から風営法の基準を意識しておくことが肝心です。
必須!キャバクラに必要な3つの主要許可とは
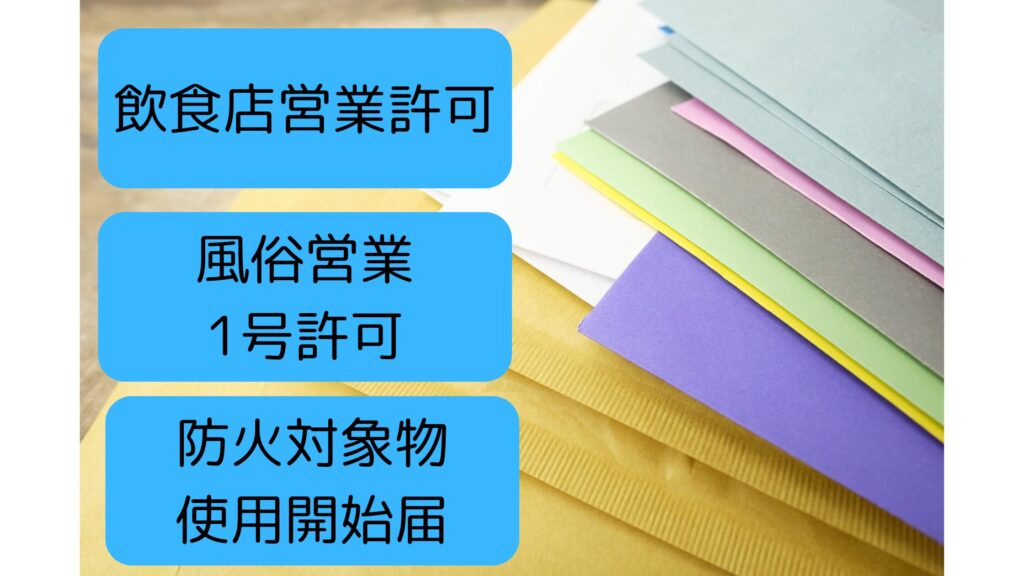
沖縄でキャバクラを営業するには、「飲食店営業許可」「風俗営業1号許可」「消防関係の届出」の3つが欠かせません。
これらはそれぞれ別の行政機関に対して申請が必要で、内容も難しく感じるかもしれませんが、ひとつひとつ確実に進めることで開業の成功につながります。
ここでは、それぞれの許可や届出について、何が必要なのか、どんな準備が求められるのかをわかりやすく解説していきます。
保健所での「飲食店営業許可」
キャバクラではお酒や料理を提供するため、飲食店としての許可が必要です。
この許可を取るには、厨房の設備や衛生面が基準を満たしているかが重視されます。
たとえば、手洗い場の設置場所や換気の状況、食器の保管方法などがチェックされます。
もし基準に合わない場合は、改善工事や再検査が必要になることもあります。
スムーズに許可を取得するには、店舗の設計段階から保健所に相談しながら進めるのが安心です。
開業準備の第一歩として、早めに保健所と連絡を取っておきましょう。
なお、各保健所の連絡先や所在地は沖縄県の公式ホームページで確認できます。
店舗所在地をもとに、該当する保健所をチェックし、必要な手続きを早めに進めましょう。
警察署への「風俗営業1号許可(キャバクラ営業許可)」
キャバクラでは、接待をともなう営業を行うため、「風俗営業1号許可」が必要です。
これは警察署を通じて、公安委員会に申請する手続きです。
図面や設備の仕様書、営業者の経歴書など、用意しなければならない書類が多く、申請の準備だけでもかなりの時間がかかります。
審査期間も2か月ほどかかるため、早めに準備を始めることが大切です。
店舗の立地条件や構造によっては、そもそも許可が下りないケースもあるため、事前の確認が欠かせません。
不安な方は、行政書士など専門家に相談するのがおすすめです。
沖縄県内の警察署では出店地域によって担当となる警察署が異なります。各警察署の管轄地域は以下のサイトからご確認ください。
消防署への「防火管理者選任届・防火対象物使用開始届」
キャバクラでは多数のお客様が出入りするため、万が一の火災に備えて消防への届出も必要です。
特に「防火管理者の選任」と「防火対象物の使用開始届」は忘れずに行いましょう。
防火管理者は、一定の広さを超える建物では必須となり、オーナーや店長が講習を受けて資格を取るのが一般的です。
また、開業前には避難経路や消火器の設置状況などを消防署が確認します。
こうした届出を怠ると、指導や営業停止の対象になることもあります。
安心して営業を始めるために、消防署への手続きも計画的に進めておきましょう。
届出や報告をおこなう消防署は出店地域によって異なります。沖縄県内における消防署の管轄地域は以下のサイトからご確認ください。
それぞれの許可を取得するための条件と注意点
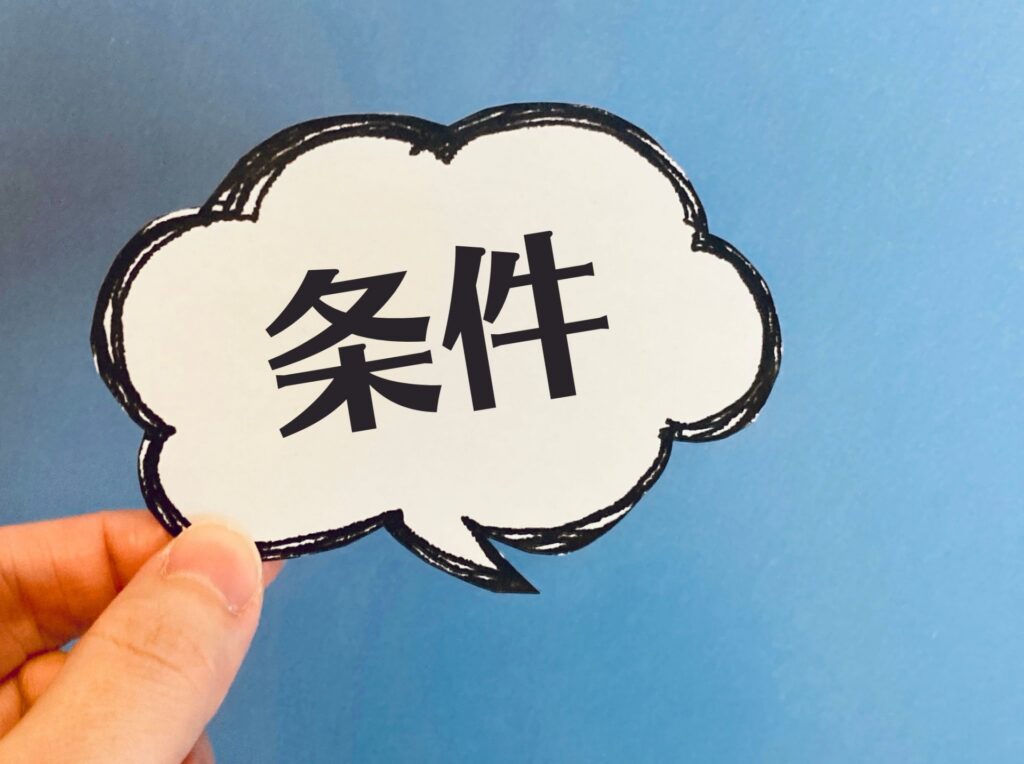
許可名が同じでも、実際に審査される内容は行政機関ごとに大きく異なります。
「あとで直せばいい」と油断すると、申請の差し戻しや追加工事で費用が膨らみがちです。
ここでは飲食店営業許可・風営法許可・消防届け出の3つについて、押さえるべき条件と落とし穴を具体的に解説します。
飲食店営業許可の取得要件と設備基準
キャバクラでも料理やドリンクを提供する以上、飲食店営業許可は避けて通れません。まずは許可を得るためのポイントを押さえましょう。
厨房には二槽シンク、手洗い器、十分な換気設備が必要です。さらに冷蔵庫や食器棚は清掃しやすい素材で統一し、害虫侵入を防ぐ網戸や扉の気密性も評価されます。
申請図面と現場が一致しないと検査で差し戻されますので、工事前に保健所へ図面を持込み確認することが安全策です。
また、調理台の高さや排水の勾配など細かな衛生基準も定められています。オープン後に改修すると余計なコストがかかります。初期段階で基準を満たす設計にすることで、許可取得もスムーズになり、開業スケジュールを守れます。
風営法許可の要件(構造基準・人的要件・立地制限など)
接待を伴うキャバクラは風営法1号許可を取得しなければ営業できません。この許可では店舗構造、人的要件、立地制限の三点が審査されます。
構造では客室1室あたり面積やパーテーションの高さ、照度など細かな数値基準があります。人的要件ではオーナーや管理者に禁錮以上の刑歴がないこと、成年後見人でないことなどが求められます。
加えて学校や病院からの距離が足りない立地では申請自体が受け付けられません。図面確認と周辺調査を開業計画の初期に行い、基準を満たす店舗を選ぶことが許可取得への近道です。
審査には約55日かかるため、他の工事日程と並行して書類作成を進めましょう。
消防署への届出時に見落としがちなポイント
消防署への届出は開業直前に慌てやすい手続きですが、安全と信頼を守る要です。まず防火管理者を選任し、講習修了証を取得してから『防火管理者選任届』を提出します。
さらに店舗を営業用に使い始める7日前までに『防火対象物使用開始届』を届けます。この際、避難経路図や消火器・誘導灯の配置図を添付する必要があります。
点検時に通路に物が置かれている、照明が非常灯に切り替わらないといった不備が見つかると改善指示を受け、オープンが遅れる恐れがあります。
事前点検チェックリストを作り、万全の状態で立会検査に臨みましょう。
自分で手続きできる?それとも行政書士に依頼すべき?
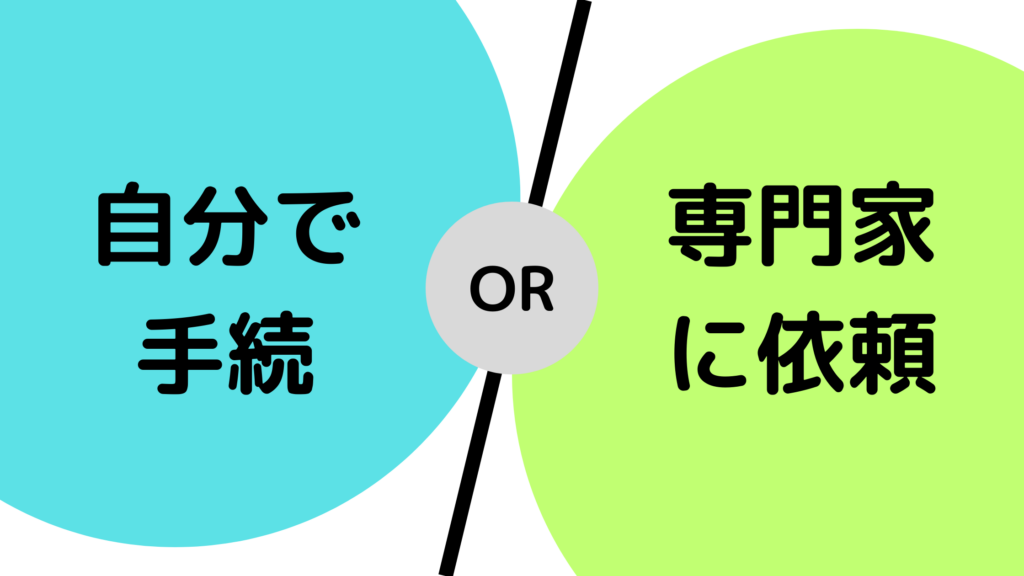
キャバクラ開業の許可申請は、「時間をかけて自分で進めるか」「費用を払って専門家に任せるか」の二択になります。
どちらにもメリットとデメリットがあるため、準備に割ける時間・資金・リスク許容度を踏まえて判断することが大切です。
手続きにかかる時間と準備の負担
キャバクラ開業の許可申請を自分で進める場合、飲食店営業許可だけでも図面作成や書類収集、保健所との調整に平均1〜2週間かかります。
そこへ風営法の書類作成や立地調査、警察とのやり取りが加わると、全体で2〜3か月は見ておく必要があります。
さらに申請後の補正依頼に対応する時間、現場検査への立ち会い、改修工事の手配も発生します。
準備期間が長引くほど家賃や人件費の先行コストが増える点には注意が必要です。
余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。
自分で行うメリット・デメリット
自分で手続きを行えば、行政書士報酬を節約できるのが最大のメリットです。
書類作成を通じて制度を深く理解できるため、開業後の軽微な変更届も自力で対応しやすくなります。
ただし専門用語の解釈ミスや書類不備による差し戻しは珍しくありません。
結果として開業が遅れ、売上機会を逃すリスクも高まります。
また、立地制限の確認漏れが後から発覚すると、物件契約の違約金まで背負う可能性もあります。
時間価値を考えると「費用を取るかスピードを取るか」の判断が必要です。慎重に検討しましょう。
専門家に依頼することで得られる安心とスピード
行政書士に依頼すると、要件チェックから書類作成、警察や保健所との折衝まで一括で任せられます。
専門家は最新の審査基準を熟知しているため、補正や再提出の可能性を大幅に減らせます。
その分、報酬は発生しますが、許可取得までの期間を1か月以上短縮できるケースも珍しくありません。
準備期間が短いほど空家賃やスタッフ待機費用を抑えられるため、最終的なコスト圧縮につながります。
何より「手続きがちゃんと通るだろうか」という精神的な負担が軽くなる点は大きなメリットです。
行政書士に依頼するメリットと費用相場

キャバクラ開業の手続きは複雑で、正確性とスピードが求められます。
そのため、行政書士に依頼してスムーズに進める方も増えています。
ここでは、行政書士に依頼することでどんな支援が受けられるのか、費用はどのくらいかかるのか、そして信頼できる専門家をどう見つければよいのかについて詳しく解説します。
行政書士に依頼すると何をしてくれるのか
行政書士に依頼する最大のメリットは、面倒な手続きの一括代行です。
飲食店営業許可や風俗営業許可の書類作成はもちろん、保健所・警察署・消防署への申請や調整も対応してくれます。
たとえば、風営法の図面作成や立地調査は専門的な知識が必要ですが、行政書士はその基準を熟知しています。
自分では見落としがちなポイントもカバーしてくれるため、許可取得までのリスクを大きく減らせます。
また、行政機関とのやり取りや修正依頼にもスムーズに対応してくれるため、精神的な負担も軽減できます。「何から始めればよいかわからない」という段階からでも安心して相談できます。
依頼する場合の費用の目安と内訳
行政書士に手続きを依頼する際の費用は、地域や事務所によって異なりますが、キャバクラ開業では総額20万〜30万円が一般的です。
内訳としては、風俗営業許可の申請サポートが20万円前後、飲食店営業許可の申請が4万円前後、図面作成や立地調査が含まれる場合は追加で数万円程度かかります。
さらに、申請時に必要な証紙代(警察への手数料)として24,000円(沖縄県の場合)が別途必要です。
「全部込みでいくらかかるのか」を事前に見積もってもらい、明細を確認することが大切です。
費用だけで判断せず、対応の丁寧さや得意分野も含めて検討すると、満足のいく依頼につながります。
当事務所では
飲食店営業許可申請 44,000円~
風俗営業1号許可申請 220,000円~
にてお手続きの代行をしております。
どんな行政書士を選べばいい?信頼できる専門家の見極め方
キャバクラの開業手続きは専門性が高いため、すべての行政書士が対応できるわけではありません。
選ぶ際は「風俗営業許可に詳しいか」「店舗系の実績があるか」を確認することが重要です。
ホームページで実績や対応分野を明示している行政書士は信頼性が高く、相談時の説明がわかりやすいかどうかも大きな判断材料になります。
「質問に丁寧に答えてくれるか」「費用の見積もりが明確か」もチェックポイントです。
また、開業後もトラブル対応や変更届などを頼める関係を築けると安心です。
一度の依頼で終わりではなく、長期的なパートナーとして考える視点で選ぶことをおすすめします。
よくあるトラブル・失敗例とその対策
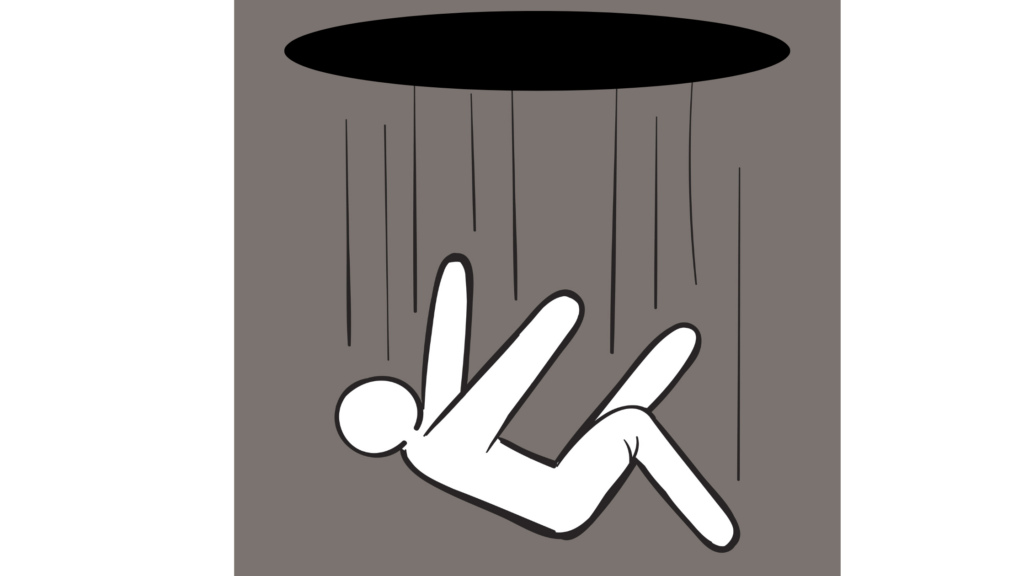
キャバクラ開業の手続きでは、思わぬところでつまずき、予定より何か月も遅れることがあります。
ここでは現場で頻発する三つの失敗例と対策を具体的にまとめました。
同じ落とし穴にはまらないよう、ぜひ参考にしてください。
「構造基準を満たさず不許可に…」設計段階での落とし穴
店舗が完成してから「壁が高すぎる」と指摘され、オープンが一ヶ月延びた例は珍しくありません。
設計段階で客室面積やパーテーション高さ、照度など風営法の数値基準を確認せずに進めると、追加工事費まで発生します。
図面を作成する前に専門家とチェックリストを共有し、仮図面の段階で保健所と警察に相談することが手戻り防止の最短ルートです。
さらにスプリンクラーの有無や動線確保も審査対象なので、初期段階で基準に適合させる設計が最も経済的です。
「立地制限で申請不可」風営法の盲点
好立地に思えた物件でも、学校から100メートル以内という理由で申請が受け付けられないケースが後を絶ちません。
風営法は病院や児童福祉施設などから一定距離を取るよう定めています。
契約前に自治体の生活安全課で用途地域と保全対象施設の位置を確認しなければ、違約金や退去費用を負担する羽目になります。
不動産業者の説明をうのみにせず、地図と条例を突き合わせる二重チェックが安全策です。
行政書士に依頼すれば距離測定図を作成してくれるため、適合可否を事前に判断できます。
申請書類の不備で遅延・再提出になるケース
誤字や押印漏れひとつで再提出となり、審査が停止することは珍しくありません。
風俗営業許可では役員全員の住民票や身分証明書、経歴書などが必要で、期限切れの書類が混じると補正通知が届きます。
提出前にチェックリストを作成し、第三者のダブルチェックを受けることでヒューマンエラーを防げます。
行政書士に任せれば最新の書式や添付書類を確認しながら作成してくれるため、補正ゼロで許可を得られる可能性が高まります。結果として時間とコストの両面を節約できます。
キャバクラ開業成功のポイント|手続き以外でやるべきこと

許可が取れても、すぐに黒字化できるとは限りません。
市場のニーズを読み、人材を整え、万一のトラブルに備えることで、ようやく継続的な利益が見込めます。
ここでは開業前後に押さえておきたい3つの実務ポイントを解説します。
開業前の市場調査と資金計画
キャバクラは立地と客層のミスマッチが利益を大きく左右します。だからこそ、開業前に市場調査を行い、需要を数字で把握することが不可欠です。
近隣店舗の価格帯や客単価、曜日別来客数を調べれば、必要な席数や営業時間の目安が見えてきます。
調査結果を基に、家賃・内装・人件費を含めた6か月分の資金計画を立てれば、予期せぬ出費にも耐えられる安全な運転資金を確保できます。
準備段階で「どこで・誰に・いくらで」提供するかを具体化することで、開業後の赤字リスクを最小限に抑えられるでしょう。
また、公庫や金融機関への融資相談は、根拠ある数字があるほど審査が通りやすくなります。
スタッフの採用と教育の準備
開業後すぐに売上を伸ばすには、スタッフの質が決め手になります。ところが、オープン直前に慌てて採用すると、接客スキルや勤怠意識にばらつきが出てトラブルの原因になりやすいです。
求人媒体を選ぶ前に、求める人物像と給与体系を明確にし、面接では笑顔やコミュニケーション力を重視しましょう。
採用後はロールプレイ研修やマニュアル共有を行い、統一された接客ルールを浸透させます。
早期に教育体制を整えておくと、口コミ評価が向上し、リピート客が増える好循環を生み出すことが可能です。研修動画を用意しておけば、シフトが合わない新人も同じ質で学習できます。
オープン後のトラブルを避けるための顧問体制構築
売上が安定しても、税務調査や労務トラブル、クレーム対応など新たな課題は次々に発生します。そのたびに慌てて専門家を探すより、開業時から税理士・社労士・行政書士の顧問契約を結んでおくと安心です。
月次レポートで数字を見える化すれば、不正や赤字を早期に発見できます。
さらに、就業規則やハラスメント窓口を整備しておくと、スタッフ間のトラブルを未然に防げます。
顧問体制はコストではなく保険と考え、長期的に店舗価値を守る仕組みとして活用しましょう。
顧問先との定期面談を設けることで、法改正や補助金情報もいち早くキャッチできます。
キャバクラ開業はプロと連携しながら準備を進めよう
キャバクラ開業には、飲食店営業許可・風俗営業1号許可・防火関係の届出といった複数の手続きが必要で、それぞれに専門的な知識や事前準備が求められます。
さらに、構造基準や立地制限などは満たさなければ許可自体が通らないため、初期段階の判断がとても重要です。
そのため、最短で安心して開業するには、行政書士など専門家との連携が欠かせません。
すべてを自分で行うのではなく、「自分でやること」「任せるべきこと」を見極めることが、成功への近道です。
たとえば、面倒な申請書類の作成や図面調整は行政書士に依頼し、自分は市場調査やスタッフ採用に専念するなど、役割分担を明確にしましょう。
まずは、行政書士による無料相談を活用し、自分の計画に何が必要かを把握するところから始めてみてはいかがでしょうか。
事前にプロの意見を聞くことで、ムダな出費や時間のロスを避け、よりスムーズなスタートを切ることができます。
「準備を効率化したい」「失敗したくない」という方にこそ、専門家との連携をおすすめします。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。



