
「沖縄で居酒屋を開業したいけど、保健所での手続きがわからなくて不安…」そんな悩みを抱えていませんか?手続きのやり方が分からなければ、開業準備がスムーズに進まず、せっかくの夢も遠のいてしまいます。
この記事を読むことで、沖縄で居酒屋を開業する際に必要な保健所での具体的な手続き方法がわかり、営業許可を取得できるようになります。保健所での申請書類の準備から、必要な資格、申請の流れまで丁寧に解説しているので、初めての方でも安心です。
適切な手続きを踏めば、開業の不安は解消され、理想の居酒屋をスタートできます。あなたの夢を形にするために、ぜひ最後までご覧ください。
沖縄での居酒屋開業には保健所の営業許可が必須
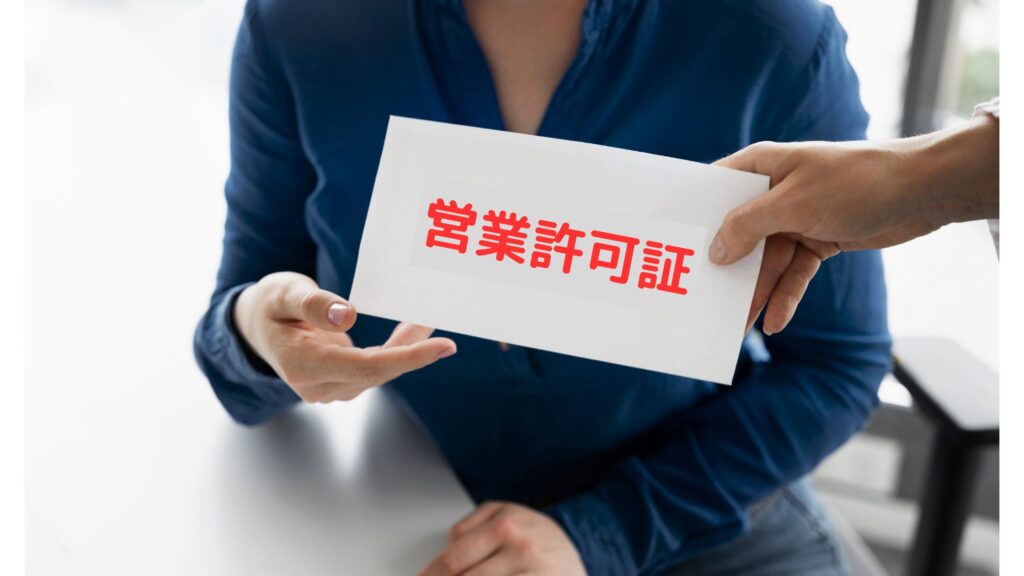
沖縄で居酒屋を開業するには、まず「保健所の営業許可」を取得する必要があります。
この許可は単なる形式ではなく、食の安全を守るための重要なチェックポイントです。
特に、店舗の設備や衛生面について細かく基準が設けられており、これを満たしていなければ営業を始めることはできません。
このセクションでは、営業許可の必要性と法律上の根拠、無許可営業のリスク、沖縄県内の保健所の情報をわかりやすく解説していきます。
なぜ保健所の許可が必要なのか?その目的と法的根拠
飲食店営業を始めるには、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。
この制度は、飲食店が不衛生な状態で営業し、食中毒や感染症を引き起こすのを防ぐために設けられています。
許可を得ることで、店舗の厨房や手洗い場、冷蔵庫などが一定の衛生基準を満たしていることが確認されます。
また、調理や接客に携わる従業員の衛生管理にも基準があり、営業前にきちんと確認される仕組みになっています。
つまり、営業許可は「安心して飲食できる環境」を整えるための出発点。
お客様に選ばれる店づくりの第一歩として、しっかりと押さえておきたい手続きです。
許可を取らずに営業した場合のリスク
営業許可を取らずに居酒屋を始めてしまうと、営業停止や罰金といった法的な処分を受ける可能性があります。
たとえ善意で営業していたとしても、無許可営業は食品衛生法違反として厳しく取り締まられます。
特に万が一、食中毒や衛生トラブルが発生した場合、保健所からの調査やメディア報道などで信用を大きく損なうリスクがあります。
その結果、営業の継続が困難になるケースも少なくありません。
さらに、開業資金をかけた内装や設備投資も無駄になってしまう恐れがあります。
リスク回避のためにも、必ず営業許可を取得してからスタートするようにしましょう。
沖縄県内の保健所の管轄区域と連絡先一覧(那覇市、南部、中部など)
営業許可の申請は、出店する地域を管轄する保健所に行います。
沖縄県では、那覇市保健所をはじめ、地域ごとにいくつかの保健所が存在します。
たとえば、那覇市内に出店する場合は「那覇市保健所」、宜野湾市や浦添市であれば「中部保健所」、南城市や八重瀬町なら「南部保健所」が窓口です。
各保健所では、事前相談や図面確認の対応も行っており、スムーズに申請するためには早めの連絡がおすすめです。
なお、各保健所の連絡先や所在地は沖縄県の公式ホームページで確認できます。
店舗所在地をもとに、該当する保健所をチェックし、必要な手続きを早めに進めましょう。
保健所の営業許可を取得するための事前準備

営業許可をスムーズに取得するには、「準備段階」がとても重要です。
申請書をいきなり提出しても、要件を満たしていなければ受理されません。
特に沖縄では、設備要件や図面の精度が厳しく見られる傾向があり、事前相談や現地の事情を踏まえた準備がカギとなります。
このセクションでは、申請前に必ずやっておくべきステップを、順を追って解説します。
事前相談は必ず行おう!相談のタイミングと流れ
営業許可を取得するには、保健所との「事前相談」が欠かせません。
図面や設備が基準を満たしていないと、申請がスムーズに通らないケースが多いからです。
事前相談では、予定している店舗の図面やレイアウトをもとに、衛生基準を満たしているかを保健所の担当者が確認してくれます。
この段階で修正の指示を受けておけば、申請後にやり直しが発生するリスクを減らすことができます。
相談のタイミングは、内装工事に着手する「前」が理想的。
予約が必要な場合もあるため、出店予定エリアの保健所に早めに連絡を取り、スケジュールを確認しましょう。
図面が超重要!求められるレベルと作成時の注意点
保健所の営業許可で最も重視されるのが「店舗の図面」です。
図面は単なる間取り図ではなく、厨房設備や手洗い場の配置、動線、給排水の位置などが正確に描かれている必要があります。
雑な手書きや簡易なスケッチでは、担当者に正確な情報が伝わらず、差し戻されることもあります。
できれば建築士や専門業者に依頼するか、パソコンソフトでの作成をおすすめします。
また、図面は「平面図」「配置図」「設備図」など複数枚求められることがあるため、保健所の指示をよく確認しましょう。
ミスや漏れがあると申請が長引く原因になるため、細部まで丁寧に準備することが大切です。
設備要件チェックリスト|シンクの数、手洗い、冷蔵庫など
飲食店として認可を受けるには、一定の設備基準をクリアしていなければなりません。
特にシンクの数や手洗い設備、冷蔵庫など、衛生管理に直結する部分は厳しくチェックされます。
たとえば、調理用とは別に「洗浄用」と「消毒用」の二槽シンクが求められることがあります。
さらに、従業員専用の手洗い器も、厨房とは別に設置する必要がある場合があります。
冷蔵庫は、食材の保管状況を見られるだけでなく、温度計の設置まで確認されることもあります。
それ以外にも、換気扇や床の排水構造、天井の防滴仕様など、見落としがちな細かい要件があります。
これらの条件は、地域の保健所によって微妙に異なることもあるため、チェックリストをもとに一つずつ確認していくことが大切です。
営業許可申請に必要な書類と提出方法
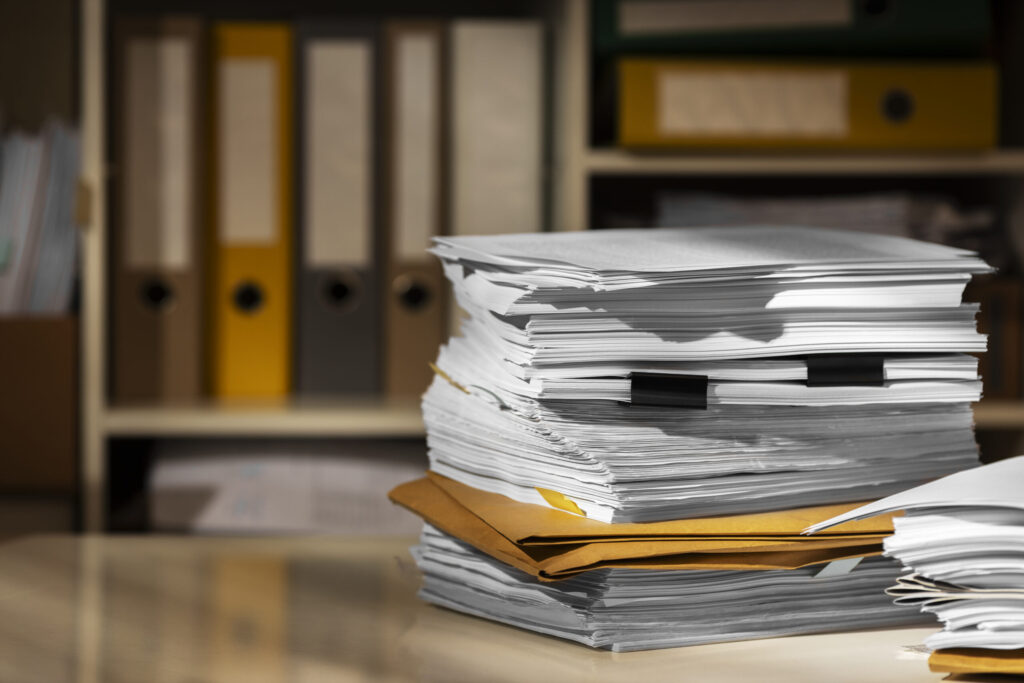
保健所の営業許可申請では、必要書類の準備と正確な提出が重要です。
書類が不足していたり内容に不備があると、申請が受理されなかったり、許可が遅れる原因になります。
このセクションでは、どんな書類が必要なのか、提出方法にはどんな選択肢があるのか、そして申請書記入時の注意点について丁寧に解説します。
これから申請を検討している方は、事前にしっかりと確認しておきましょう。
提出が必要な主な書類一覧(図面、申請書、賃貸契約書など)
営業許可を申請する際には、複数の書類を揃える必要があります。
主に必要となるのは、申請書、店舗の図面(平面図・設備図など)、施設の賃貸契約書(もしくは使用許可書)、食品衛生責任者の資格証明書の写しです。
このほか、内装工事の計画がある場合は工事スケジュール表や、既存店舗を引き継ぐ際には以前の営業許可証の写しが求められることもあります。
書類は1つでも不足すると受付ができません。
提出前にチェックリストを活用し、記載内容や添付資料に漏れがないかを確認することが、スムーズな手続きにつながります。
提出方法|持参か郵送か?予約は必要?
営業許可の申請方法には、「保健所への持参」と「郵送」の2通りがあります。
ただし、多くの保健所では持参による申請が基本となっており、事前予約が必要な場合がほとんどです。
那覇市や中部保健所などでは、混雑を避けるために電話またはインターネットによる事前予約を推奨しています。
予約をしないと当日受け付けてもらえない場合もあるため、申請日が決まったら早めに連絡しましょう。
また、郵送での申請を受け付けていない保健所もあるため、事前に確認が必要です。
いずれの場合も、提出後に内容確認や修正依頼が入ることがあるため、時間に余裕を持った行動が大切です。
営業許可申請書の記入ポイントとよくあるミス
申請書の記入は、丁寧かつ正確であることが求められます。
店名や代表者名、所在地などの基本情報に加え、調理設備や従業員数など細かな項目も記載が必要です。
記入ミスで特に多いのが、住所の番地抜けや面積の単位ミス、調理区画の表記漏れです。
また、設備名に専門用語を使わずに記入したために、内容が正確に伝わらず、確認のために再提出となるケースもあります。
不安な方は、保健所で配布されている記入例を参考にしながら進めると安心です。
提出前には、第三者の目でもう一度確認してもらうと、記入ミスを防ぎやすくなります。
居酒屋の営業許可取得には欠かせない食品衛生責任者の資格

営業許可を取得する際、店舗ごとに「食品衛生責任者」を配置することが法律で定められています。
これは保健所の許可を受ける上での必須条件となるため、無資格のままでは開業手続きが進められません。
このセクションでは、食品衛生責任者とは何か、資格を持っていない場合の取得方法、そして講習のスケジュールや費用についてわかりやすく解説します。
事前に資格取得を計画しておくことで、開業準備がスムーズに進みます。
食品衛生責任者とは?取得条件と講習内容
食品衛生責任者は、飲食店など食品を扱う施設に1名以上配置が義務付けられている衛生管理の担当者です。
この資格を持つことで、店舗の衛生状態を維持・監督する役割を担うことになります。
資格取得の条件に特別な学歴や経験は不要で、講習会を受講することで誰でも取得できます。
講習は1日で完結し、内容は食中毒の予防や衛生管理、食品表示など、飲食店に必要な知識が網羅されています。
開業の前にこの講習を受けておくことで、保健所への申請時にも安心して手続きを進めることができます。
資格を持っていない場合の取得方法(沖縄県の講習情報)
資格を持っていない場合は、沖縄県内で実施されている「食品衛生責任者養成講習会」に参加すれば取得可能です。
講習会は沖縄県食品衛生協会が各地域の保健所と連携して定期的に開催しており、事前予約制での受付となっています。
申込方法は、協会の公式サイトや窓口で申請書を提出する形が一般的です。
講習は1日で終了し、修了証をその場で交付してもらえることが多く、すぐに営業許可申請に使うことができます。
定員制のため、開業予定が決まったら早めに日程を確認して予約するのがポイントです。
特に繁忙期はすぐに満席になることがあるため、余裕を持った計画が求められます。
参考:沖縄県 食品衛生責任者 養成講習会開催日程 | 沖縄県食品衛生協会
資格取得のスケジュールと費用
食品衛生責任者の資格取得は、1日の講習を受けるだけで完了します。
そのため、開業までに比較的スムーズに取得できる資格のひとつといえます。
講習は沖縄県内で月に数回程度実施されており、受講日程は沖縄県食品衛生協会のホームページで公開されています。
日程や会場を確認したうえで、空き状況をチェックし、早めに申し込んでおくのが安全です。
受講料は概ね1万円前後が相場となっており、比較的手頃な費用で取得できます。
この費用と1日のスケジュールをしっかり押さえておけば、営業許可の取得準備も順調に進められるでしょう。
申請から許可が出るまでの流れと期間

営業許可は申請して終わりではなく、現地検査や結果通知までの一連の流れがあります。
このプロセスを正しく理解しておくことで、開業スケジュールに無理がなく、慌てず準備を進められます。
このセクションでは、申請から現地検査までの流れ、許可が出るまでの日数、そして開業日を決める際に注意すべきポイントを解説します。
開業までの時間をムダにしないために、ぜひ参考にしてください。
申請から現地検査までのスケジュール感
営業許可の申請を保健所に提出すると、まず日程調整のうえで現地検査が実施されます。
通常、申請書を提出してから3日〜1週間以内に保健所の担当者から連絡が入り、検査日が決まります。
検査当日は、保健所の職員が厨房や設備の状況を確認し、図面と実際の設計に相違がないかをチェックします。
もし不備や改善点が見つかった場合、再検査や写真提出などが必要になることもあります。
スムーズに進めるためには、申請前の事前相談と、申請時の正確な書類作成がとても重要です。
開業準備に余裕を持つためにも、検査までの1週間程度は見込んでおきましょう。
営業許可が出るまでにかかる日数の目安
現地検査が無事に終了すると、営業許可証が交付されます。
許可が下りるまでの期間は、検査日から通常3〜7営業日ほどです。
ただし、申請が集中する時期や不備があった場合は、それ以上かかることもあります。
この期間中に、保健所から追加の資料提出や軽微な修正を求められることがあります。
そのため、常に電話やメールにすぐ対応できるようにしておくと安心です。
許可証が交付されるまでは営業を始めることはできないため、オープン日を決める際はこの日数を逆算して準備を進めましょう。
余裕のあるスケジューリングが、トラブル回避につながります。
開業スケジュールを組むときの注意点
開業スケジュールを組む際には、「許可が下りるまでの待機期間」も見越すことが必要です。
設備工事が予定より長引いたり、保健所とのやり取りに時間がかかることもあるからです。
とくに内装工事の完了が遅れると、検査日の調整や申請そのものが遅れるため、開業日がずれ込む可能性が高まります。
また、許可が出るまでは食材の仕入れや告知を控えるのが無難です。
スムーズな開業のためには、申請から許可取得までに最低でも3〜4週間の余裕を持ってスケジュールを立てましょう。
「早め早め」の行動が、結果的にコストとストレスの軽減につながります。
営業許可の取得にかかる費用

居酒屋を開業する際は、設備や仕入れだけでなく、営業許可の取得に関する費用も事前に見積もっておく必要があります。
営業許可の申請手数料はもちろん、図面作成や資格講習、さらには専門家に依頼した場合の報酬など、複数の出費が重なります。
このセクションでは、実際にどのくらいの費用がかかるのかを具体的に整理し、準備すべき予算の目安をわかりやすく解説します。
営業許可申請にかかる手数料(沖縄県の料金例)
営業許可の申請には、各自治体ごとに定められた手数料が必要です。
沖縄県では、一般的な飲食店(飲食店営業)の場合、申請手数料は16,000円となっています(2025年7月時点の那覇市保健所の例)。
この手数料は1店舗あたりの金額であり、複数の営業形態を申請する場合は別途追加費用がかかることもあります。
申請時に一括納付する必要があるため、開業予算に組み込んでおくことが大切です。
また、仮に申請が却下された場合でも返金されないため、提出書類の不備がないよう事前確認は怠らないようにしましょう。
その他、図面作成や資格講習などにかかる実費
営業許可の取得に関連して発生する費用は、手数料だけではありません。
たとえば、店舗の図面をプロに依頼する場合、簡易なレイアウトでも1〜3万円ほどかかることがあります。
また、食品衛生責任者の資格を持っていない場合は、養成講習の受講料が発生します。
沖縄県内では約10,000円前後が相場で、受講日には交通費や食事代などの出費も見込まれます。
このような実費は地味にかさみやすく、予算を圧迫する要因となるため、あらかじめ一覧で整理し、余裕を持った資金計画を立てておくことが重要です。
専門家に依頼する場合の費用相場
営業許可申請をスムーズに進めたい場合、行政書士などの専門家に手続きを依頼する選択もあります。
その際の費用は事務所や依頼内容によって異なりますが、沖縄県内では概ね30,000〜60,000円前後が相場とされています。
この費用には、申請書の作成、図面の整備支援、保健所とのやり取りなどが含まれることが一般的です。
時間や手間を節約できる一方で、当然コストはかかるため、自分でできる部分とのバランスを考えて検討しましょう。
不安な点が多い方やスケジュールに余裕がない方は、専門家に任せることでトラブルを防げる可能性も高まります。
保健所以外で必要な手続きにも注意

居酒屋の開業準備では、「保健所での営業許可」だけに気を取られがちですが、それ以外にも法律で定められた重要な手続きがあります。
これらを怠ると、開業後に思わぬトラブルにつながる可能性があります。
このセクションでは、深夜営業や消防関係、税務署への届出、従業員を雇う場合に必要な手続きまで、保健所以外で対応すべき主な項目をわかりやすくまとめました。
抜け漏れなく準備を進めていきましょう。
飲食店営業許可の他に必要な主な手続き一覧(深夜営業、風営法、消防など)
営業許可を取得しても、営業形態によっては追加の手続きが求められます。
たとえば、深夜0時以降も営業する居酒屋は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。
これは風営法の対象となり、所轄の警察署へ届出を行わなければなりません。
さらに、店内で音楽演奏やカラオケを行う場合も、別途の許可や届出が必要となる場合があります。
消防署への「防火対象物使用開始届」や、「消防設備の設置・点検報告」も義務です。
これらの手続きを怠ると、行政処分や営業停止のリスクがあるため、開業エリアの所轄機関に事前確認をしておきましょう。
事業開始届・税務署への手続き
居酒屋を開業する際は、税務署への「開業届」の提出も忘れてはいけません。
個人事業主であれば「個人事業の開業・廃業等届出書」を、法人であれば「法人設立届出書」をそれぞれ開業日から1か月以内に提出する必要があります。
この届出を行うことで、青色申告の申請や、各種税制上の優遇措置が受けられるようになります。
特に青色申告は節税メリットが大きいため、併せて「青色申告承認申請書」の提出もおすすめです。
開業後の会計処理をスムーズに進めるためにも、開業届の提出タイミングと必要書類はしっかり押さえておきましょう。
労働保険・社会保険・雇用契約の準備
従業員を1人でも雇う場合、労働保険と社会保険の加入が義務になります。
労災保険と雇用保険の「労働保険」は、原則として雇用開始後10日以内に手続きを行います。
また、従業員が正社員や勤務日数の多いパートであれば、健康保険・厚生年金といった「社会保険」への加入も必要です。
これらの手続きを怠ると、労基署や年金事務所から是正指導を受けるリスクがあります。
さらに、雇用契約書の作成や就業規則の整備も、トラブル防止のために重要です。
人を雇うなら、開業と同時に労務管理体制も整えておきましょう。
手続きが不安な方へ|専門家への依頼も検討しよう

飲食店の開業準備は、保健所での手続きをはじめ、消防署や警察署、税務署など、複数の機関とのやり取りが必要になります。
そのため、「自分で全部やるのは難しそう」と感じる方も少なくありません。
このセクションでは、どこまでを自分で進め、どこからを専門家に依頼すべきかを整理し、行政書士に依頼するメリットと注意点、信頼できる専門家の探し方について紹介します。
効率よく開業準備を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
どこまでを自分でやって、どこからを依頼すべき?
飲食店の開業準備は、手続きの量も内容も想像以上に多岐にわたります。
中でも、図面作成や営業許可申請、深夜営業届などは専門知識が求められる場面が多く、慣れていないと時間も手間もかかります。
一方で、食品衛生責任者の講習受講や税務署への開業届の提出など、比較的わかりやすい手続きは自分でも対応可能です。
そのため、重要な部分や初めての手続きに限って専門家に依頼し、他は自力で進めるという分担も選択肢になります。
開業スケジュールや費用の状況を踏まえ、自分に合ったやり方を考えてみましょう。
行政書士に依頼するメリットと注意点
行政書士に手続きを依頼する最大のメリットは、「安心して本業の準備に集中できること」です。
営業許可の図面確認や保健所とのやり取り、書類の記入補助などを一括で任せられるため、申請ミスや抜け漏れを防ぐことができます。
また、地域に詳しい行政書士であれば、保健所ごとのローカルルールや担当者の傾向まで把握しているため、よりスムーズな申請が可能になります。
一方で、業務範囲外の相談(税務・経理・補助金など)には対応できないこともあるため、事前に対応範囲や料金体系をしっかり確認しておくことが重要です。
信頼関係を築ける行政書士と出会うことが、成功の第一歩になります。
沖縄県内で飲食店開業に強い専門家を探すには?
沖縄県内で飲食店開業に強い専門家を探すには、いくつかの方法があります。
まずは「行政書士会の公式サイト」や「商工会議所」で検索・紹介を受けるのが確実です。
実績や得意分野が明記されている事務所も多く、飲食店に特化したサポートを行っている専門家を見つけやすくなります。
そのほか、地域密着型の開業支援セミナーや補助金説明会では、実際に開業サポートを行っている行政書士が講師を務めていることもあります。
直接話を聞けるチャンスなので、参加してみるのもおすすめです。
口コミやSNSでの評価も参考にしながら、相性の良い専門家をじっくり選びましょう。
スムーズに保健所の手続きを終わらせて、理想の居酒屋開業を!
沖縄で居酒屋を開業するには、まず保健所での営業許可申請が必須です。
そのためには、設備や図面の基準をクリアし、必要な書類をそろえて申請を行う必要があります。
さらに、食品衛生責任者の資格取得や、深夜営業・消防・税務署への届出など、保健所以外の手続きにも対応しなければなりません。
これらの準備をすべて自分で行うことは可能ですが、時間や労力、知識が求められる場面も多いため、不安を感じる方も少なくないでしょう。
特に初めての開業では「知らなかった」ことがトラブルにつながるケースもあります。
だからこそ、要所では行政書士などの専門家の力を借りるのも有効な選択肢です。
地域のルールや申請の流れを熟知した専門家なら、あなたの開業準備をしっかりサポートしてくれるはずです。
手続きをスムーズに終わらせ、理想のお店づくりに集中するためにも、まずは信頼できる専門家への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
当事務所はどんなご相談でも丁寧にお話をおうかがいします。
初回無料となっておりますので、ささいなご相談でもお気軽にお問い合わせください。



